今回は『更級日記』の「源氏の五十余巻」を解説していきたいと思います。
文学史
作者
菅原孝標女
成立
1060年頃
ジャンル
日記
内容
約40年に渡る半生を回想した自伝的日記。
『源氏物語』に憧れる少女時代が描かれる。また、菅原孝標女は『蜻蛉日記』の作者である藤原道綱母の姪である。
本文
その春、世の中いみじう騒がしうて、松里のわたりの月影あはれに見し乳母も、三月朔日に亡くなりぬ。
せむ方なく思ひ嘆くに、物語のゆかしさもおぼえずなりぬ。
いみじく泣き暮らして、見出だしたれば、夕日のいと華やかにさしたるに、桜の花残りなく散り乱る。
散る花もまた来む春は見もやせむ やがて別れし人ぞ恋しき
また聞けば、侍従の大納言の御女、亡くなり給ひぬなり。
殿の中将の思し嘆くなるさま、わがものの悲しき折なれば、いみじくあはれなりと聞く。
上り着きたりし時、
「これ手本にせよ。」
とて、この姫君の御手を取らせたりしを、
「小夜ふけて寝ざめざりせば」
など書きて、
「鳥辺山谷に煙の燃え立たば はかなく見えし我と知らなむ」
と、言ひ知らずをかしげにめでたく書き給へるを見て、いとど涙を添へまさる。
かくのみ思ひくんじたるを、心も慰めむと、心苦しがりて、母、物語など求めて見せ給ふに、げにおのづから慰みゆく。
紫のゆかりを見て、続きの見まほしくおぼゆれど、人語らひなどもえせず。たれもいまだ都慣れぬほどにて、え見つけず。いみじく心もとなく、ゆかしくおぼゆるままに、この源氏の物語、一の巻よりしてみな見せ給へと、心の内に祈る。
親の太秦に籠り給へるにも、ことごとなく、このことを申して、出でむままにこの物語見果てむと思へど、見えず。
いとくちをしく思ひ嘆かるるに、をばなる人の、田舎より上りたる所にわたいたれば、「いとうつくしう生ひなりにけり。」など、あはれがり、めづらしがりて、帰るに、「何をか奉らむ。まめまめしきものは、まさなかりなむ。ゆかしくし給ふなるものを奉らむ。」とて、源氏の五十余巻、櫃に入りながら、在中将・とほぎみ・せりかは・しらら・あさうづなどいふ物語ども、一袋取り入れて、得て帰る心地のうれしさぞいみじきや。はしるはしる、わづかに見つつ、心も得ず、心もとなく思ふ源氏を、一の巻よりして、人もまじらず、几帳の内にうち伏して引き出でつつ見る心地、后の位も何にかはせむ。
昼は日暮らし、夜は目の覚めたる限り、灯を近くともして、これを見るよりほかのことなければ、おのづからなどは、そらにおぼえうかぶを、いみじきことに思ふに、夢に、いと清げなる僧の、黄なる地の袈裟着たるが来て、「法華経五の巻を、とく習へ。」と言ふと見れど、人にも語らず、習はむとも思ひかけず。物語のことをのみ心にしめて、我はこのごろわろきぞかし、盛りにならば、かたちも限りなくよく、髪もいみじく長くなりなむ、光の源氏の夕顔、宇治の大将の浮舟の女君のやうにこそあらめ、と思ひける心、まづいとはかなく、あさまし。
現代語訳
その(翌年の)春は、世の中に伝染病が流行して、松里の渡し場の月の光に照らし出されたその姿を(私が)しみじみと悲しい思いで見た乳母も、三月一日に亡くなってしまった。
どうしようもなく嘆き悲しんでいると、物語を見たいという気持ちもなくなってしまった。
ひどく泣き暮らして、外を見やったところ、夕日がたいそう華やかにさしている辺りに、桜の花が残りなく散り乱れている。
(今は)散ってゆく桜の花も、また来年の春には見ることができるだろう。しかし、(松里で別れて)そのまま永遠の別れとなってしまった乳母には、再び会うこともできず、恋しくてならない
また聞くところによると、侍従の大納言の御娘も、亡くなられたということだ。
(夫である)殿の中将がお嘆きになるというそのご様子について、私自身も(乳母の死に遭い)悲しく感じている時なので、たいそうお気の毒なことだと(思って)聞く。
上京した時に、(ある人が私に)「これをお手本にしなさい。」と言って、この姫君の書かれた御手跡を与えたが、
それに「小夜ふけて寝ざめざりせば(夜がふけて、目が覚めなかったならば)」などと(古歌が)書いてあって、(また)
「もし、鳥部山の谷に、火葬の煙が立ちのぼったならば、それは、日ごろから弱々しげで長生きしそうになく見えた私の火葬の煙なのだと思ってほしい。」
と、なんとも言えないほど趣深く美しく書いていらっしゃったのを(改めて)見て、ますます涙が流れ募る。
ただもうこんなふうにふさぎ込んでばかりいるので、(私の)心をなんとか慰めようと、心配して、母が、物語などを探してきて見せてくださったところ、なるほど心が自然と慰んでゆく。
「紫のゆかり」を見て、(物語の)続きが見たいと思われるけれど、人に相談することもできない。(家の者は皆、)誰もまだ都に慣れていない頃で、(見たい物語を)見つけ出すこともできない。たいそうじれったくて、(物語の続きを)見たくてたまらないので、「この源氏の物語を、一の巻から、全部お見せください。」と、心の中で祈る。
親が太秦に参籠なさっていた時にも(お伴をして)、ほかのことには触れずにこのことばかりをお願い申し上げて、寺を出たならすぐにこの物語を全て見てしまおうと思うけれど、(実際はそうたやすく)見ることはできない。
とても残念で、思い嘆かずにはいられない頃に、おばにあたる人で地方から上京してきた人の所に(親が私を)行かせたところ、「とてもかわいらしく成長したことだわ。」などと、懐かしがり珍しがって、 私が)帰る時に、「何を差し上げましょうか。実用向きのものではきっとつまらないでしょうね。(あなたが)見たいと思っていらっしゃると聞いているものを差し上げましょう。」と言って、『源氏物語』の五十巻余りを、櫃に入ったままで(そっくりと)、(それに加えて)「在中将」「とほぎみ」「せり河」「しらら」「あさうづ」などという物語の数々を、いっしょに一つの袋に入れて、それを手に入れて帰る時の私のうれしさはそれはもうたいへんなものであったよ。
胸をわくわくさせてごく一部を見ては、筋がわからないで納得がゆかず、もどかしく思っていた『源氏物語』を、最初の巻から、他の人にも邪魔されずに(たった一人で)、几帳の中で前にのめるようにして楽な姿勢をとって(櫃の中から)引き出しては見る気持ちに比べたら、后の位もいったい何ほどのものであろうか(いや、何ほどのものでもない)。
昼は一日中、夜は目が覚めている間ずっと、明かりを近くに灯して、この物語を見る以外ほかのことはしないので、自然と、(物語の文章が)そらで思い浮かぶのを、ほんとうにすばらしいことのように思っていると、(ある夜の)夢に、とても清楚な感じの僧で、黄色の地の袈裟を着ている人がやって来て、「『法華経』の第五巻を早く習いなさい。」と言ったと見たけれども、誰にも話さず、それを習おうとも思い寄らなくて、物語のことだけしか念頭になく、私は今はまだ(幼いから)器量がよくないのだわ、(でも)年ごろになったならば、顔立ちもこの上なくよくなり、髪もきっとたいそう長くなるに違いない、光源氏の寵愛を受けた夕顔や、宇治の薫大将に愛された浮舟の女君のようにきっとなるのだろうと思っていた(私の)心は、(今になって考えてみると)まずもって実にたわいなくあきれはてたものであった。
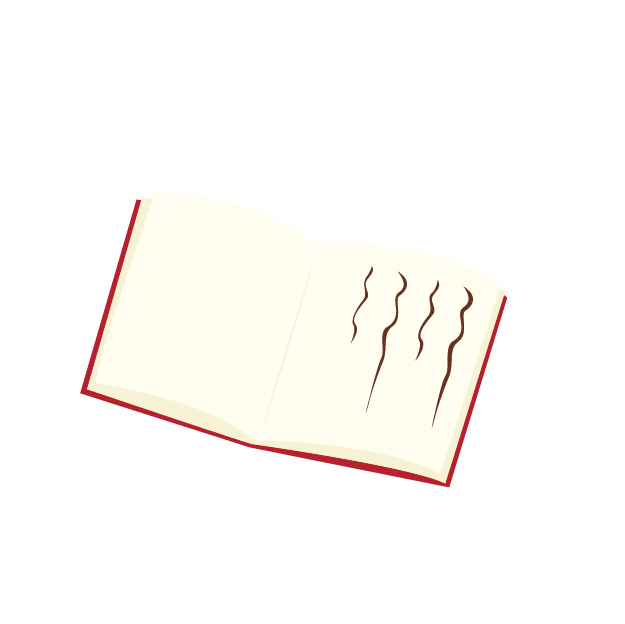

コメント