今回は『建礼門院右京大夫集』の「なべて世のはかなきことを」を解説していきたいと思います。
文学史
作者
藤原伊行女
成立
鎌倉時代初期
ジャンル
私家集
内容
長文の詞書が多く、日記的性格が強い。
建礼門院に仕えた作者が、平資盛との愛と別れや平家の滅亡などを老後に回想したもの。
本文
またの年の春ぞ、まことにこの世のほかに聞き果てにし。
そのほどのことは、まして何とかは言はん。みなかねて思ひしことなれど、ただほれぼれとのみおぼゆ。あまりにせきやらぬ涙も、かつは見る人もつつましければ、何とか人も思ふらめど、
「心地のわびしき。」
とて、引きかづき、寝暮らしてのみぞ、心のままに泣き過ぐす。
いかでものをも忘れむと思へど、あやにくに面影は身に添ひ、言の葉ごとに聞く心地して、身を責めて、悲しきこと言ひ尽くすべき方なし。ただ、限りある命にて、はかなくなど聞きしことをだにこそ、悲しきことに言ひ思へ、これは、何をかためしにせんと、返す返すおぼえて、
なべて世のはかなきことを悲しとはかかる夢見ぬ人や言ひけん
ほど経て、人のもとより、
「さても、このあはれ、いかばかりか。」
と言ひたれば、なべてのことのやうにおぼえて、
悲しともまたあはれとも世の常に言ふべきことにあらばこそあらめ
現代語訳
その翌年の春こそ、本当に(愛するあの方〈=平資盛〉が)この世以外の者となった(=亡くなった)と聞いてしまった。その(悲報を耳にした)時のことは、(それまでにも)まして何と言おうか(、何とも言いようがない)。すべて以前から覚悟していたことではあるけれど、ただ茫然とするばかりであった。あまりに抑えきれない涙も、一方では(傍らで)見る人にも遠慮されるので、どうしたのかと(周りの)人も思っているだろうけれど、「気分が悪いので。」と言って、(着物を)引きかぶって、一日中横になっていて、思いのままに泣いて過ごす。何とかして忘れてしまおうと思うのだが、意地悪くも(あの方の)面影が我が身に寄り添い、(昔聞いたあの方の)一言一言を耳に聞くような気がして、我が身を責めさいなむようで、その悲しさは十分に言い表すことのできる術もない。ただ、天寿を全うして、亡くなったなどと聞いた場合でさえ、(世間では)悲しいことと言ったり思ったりするのに、この場合は、何を例にしたらいいのであろうか(、いや例にすべきものはない)と繰り返し思われて、
おしなべて世の中の人たちが死というものを悲しいと言うのは、このような夢としか思えないほどにつらい目に遭ったことのない人が言ったのだろうか
時が経って、ある人のもとから、「それにしても、このたびのあわれさは、どれほどでしょうか。」と言ってきたので、通り一遍の(おざなりな挨拶の)ように思われて、
(今回のことは)悲しいともまたあわれとも、世間で当たり前に言えることならばぜひそうあってほしいものですが、とてもそのように言えるようなものではないのです。
(と、歌に詠んだのだった。)
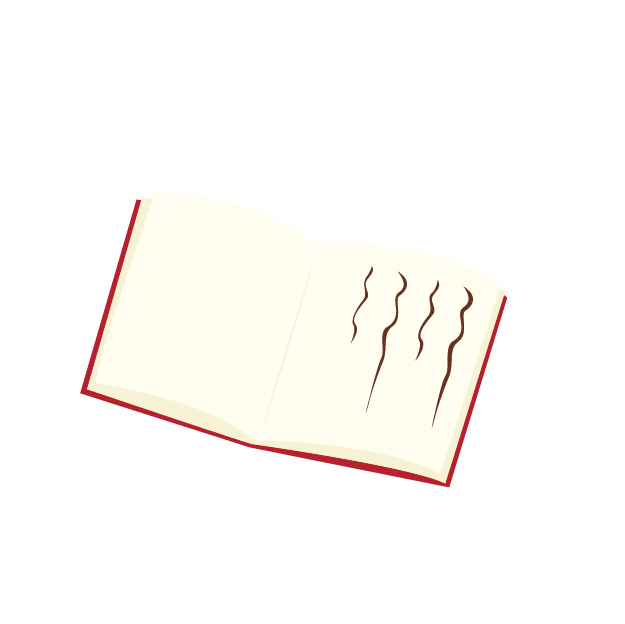

コメント