古典文法の学習に入る前に、まず抑えておくべき重要なことを。
文法の授業でよく出てくる「用言・体言・活用・活用形」など、言葉の意味を知らなければ、授業もチンプンカンプンですよね?
基礎の基礎をしっかり抑えておきましょう。
用言と体言とは?
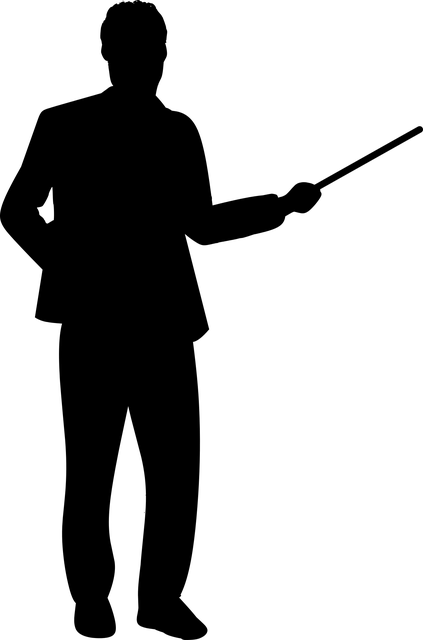
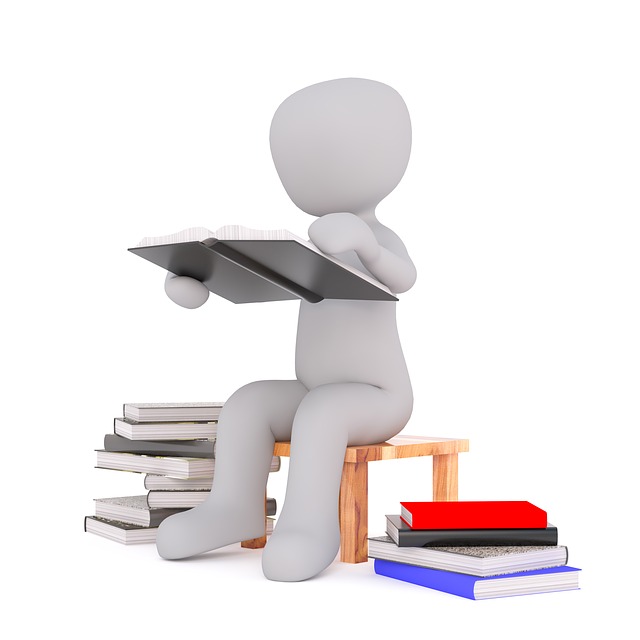
聞いたことはあるんですけど、説明するのはちょっと・・・
用言・・・活用するもの(動詞・形容詞・形容動詞)
体言・・・活用しないもの(名詞)
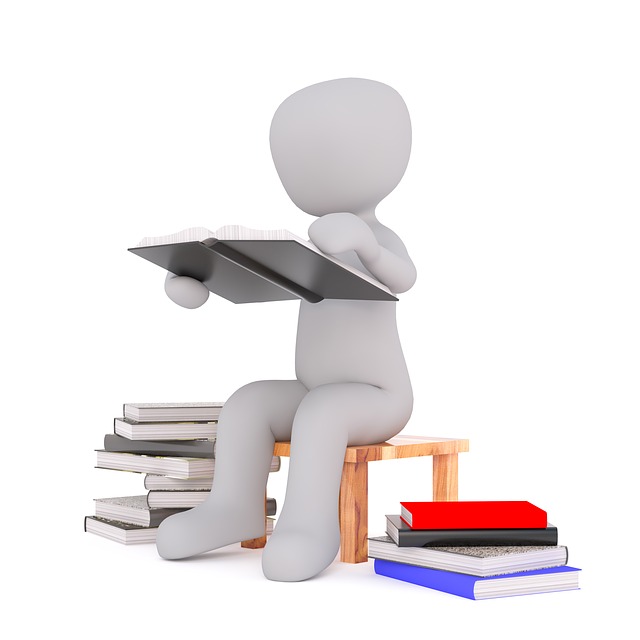
なるほど!「活用」するのか、しないのかで分けられるんですね!
でも、「活用」ってなんでしたっけ?
活用とは?
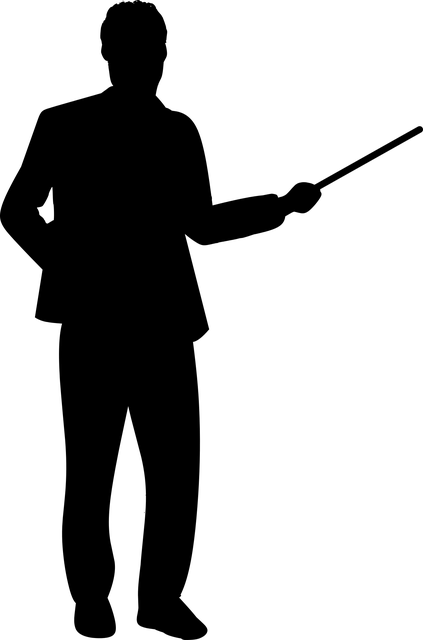
じゃあ、「書く」という動詞に「ない」を付けたら何て言うかな?
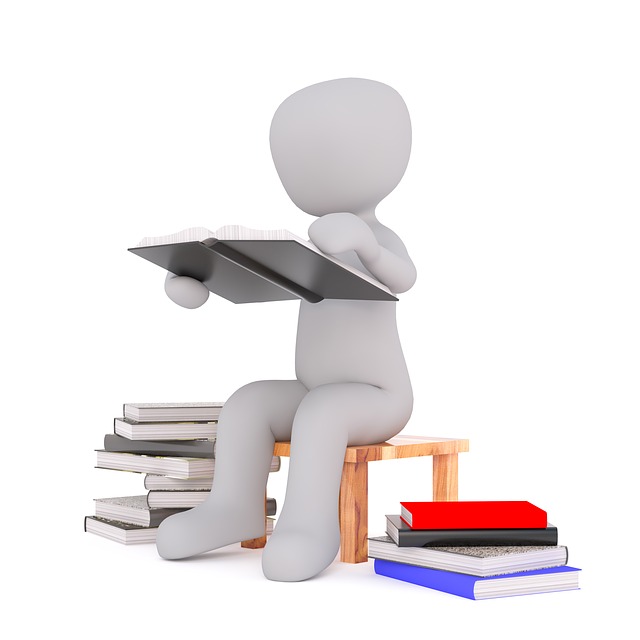
「書かない」ですね!
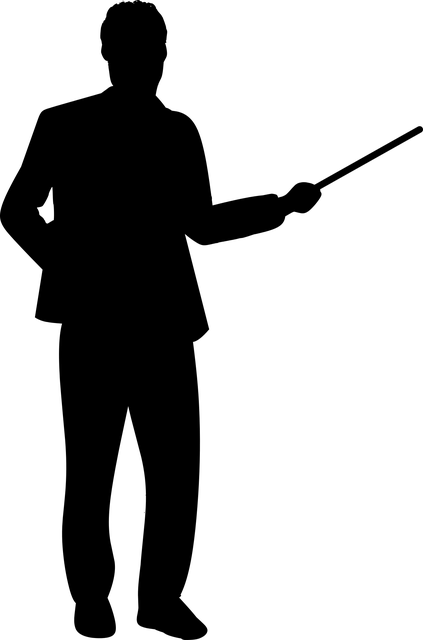
そうだね!
次は「本」という名詞に「ない」を付けるとどうだろう?
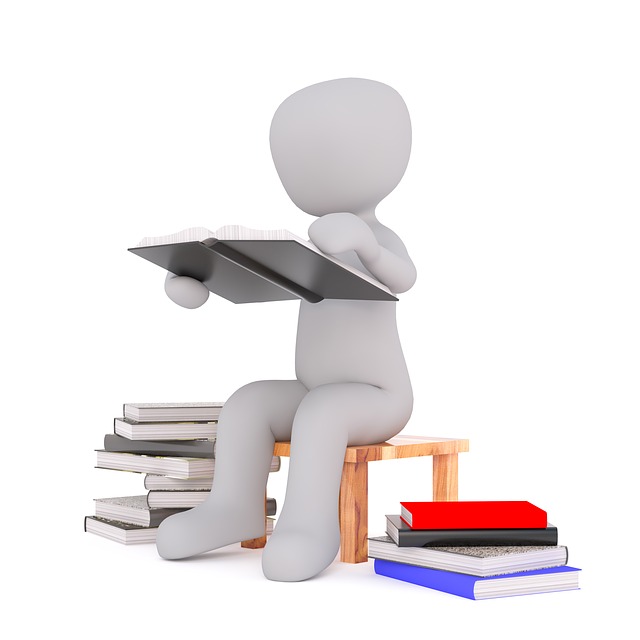
「本がない」じゃないですか?
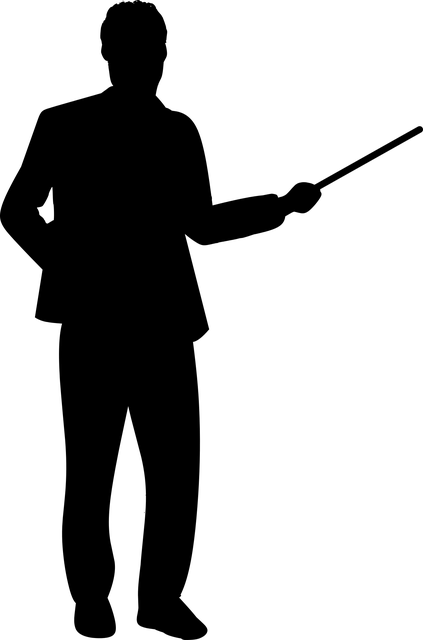
たしかにそう言うんだけど、「活用」というテーマで考えると
それは間違いなんだ。
「書く」という動詞は「ない」という言葉が続いた時、「書く」という言葉自体が変化してくっついていました。
例えば、「書かない」「書きます」「書く時」「書けば」「書こう」などのように。
この、元の言葉自体が変化して、下に続く語とくっつくことを活用すると言います。
一方で「本」という名詞は、「が」という助詞の助けを借りることで「ない」とくっついています。
こちらは、元の「本」という言葉自体が変化していないので、活用しないと言えます。
活用形とは?
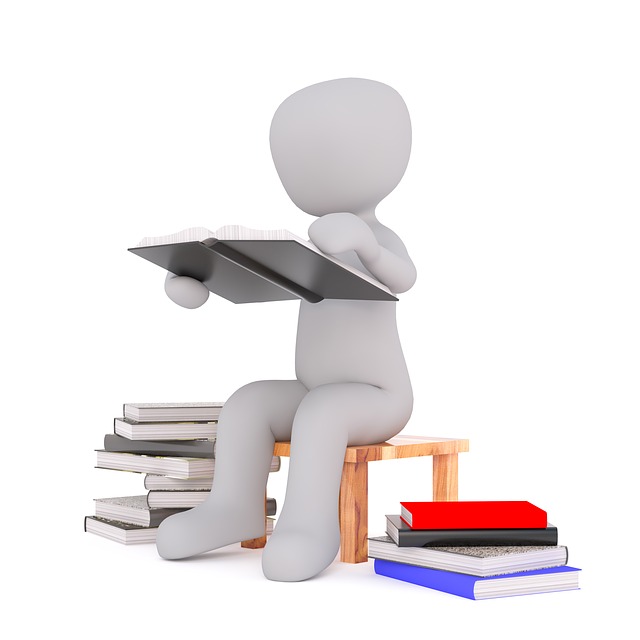
じゃあ、「活用形」っていうのは何ですか?
先程の、「書かない」「書きます」「書く時」「書けば」「書こう」などのように、「書く」が「か、き、く、け、こ」と変化する時、それぞれの形を未然形、連用形・・・などと呼び、これが活用形です。
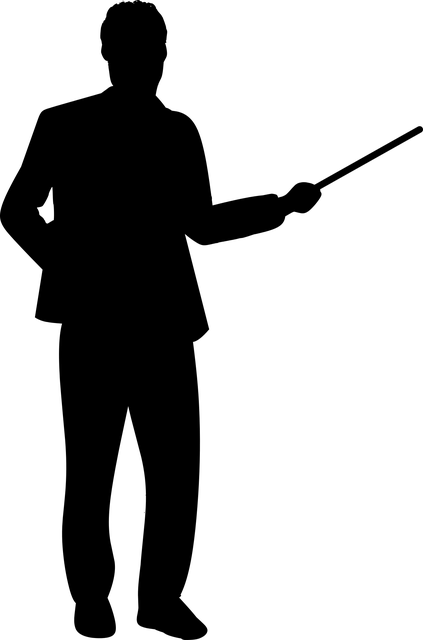
古文の活用形は「未然形・連用形・終止形・連体形・已然形・命令形」の
6種類あるよ!
まとめ
ということで、今回は文法の基礎をお伝えしました。
動画では他にも、歴史的仮名遣いや語幹、活用語尾なども解説していますので、合わせてご覧ください!



コメント