今回は『源氏物語』の「廃院の怪」を解説していきたいと思います。
文学史
作者
紫式部
成立
1008年頃
ジャンル
物語
内容
全54帖。最後の10巻きを「宇治十帖」と呼ぶ。
主人公である光源氏の一生を描く正編と、没後の子どもたちの世代を描く続編から成る。
源氏物語は、作り物語の伝奇性と歌物語の叙情性などを受け継ぎ完成された作品で日本文学の最高傑作と呼ばれる。
江戸時代の国文学者本居宣長は、『源氏物語』の本質を「もののあはれ」ととらえ評価した。
本文
宵過ぐるほど、すこし寝入り給へるに、御枕上にいとをかしげなる女居て、
「おのがいとめでたしと見奉るをば尋ね思ほさで、かく異なることなき人を率ておはして時めかし給ふこそ、いとめざましくつらけれ。」
とて、この御かたはらの人をかき起こさむとすと見給ふ。物に襲はるる心地して、驚き給へれば、灯も消えにけり。うたて思さるれば、太刀を引き抜きてうち置き給ひて、右近を起こし給ふ。これも恐ろしと思ひたるさまにて参り寄れり。
「渡殿なる宿直人起こして、紙燭さして参れと言へ。」
とのたまへば、
「いかでかまからむ、暗うて。」
と言へば、
「あな若々し。」
とうち笑ひ給ひて、手を叩き給へば、山彦の答ふる声いと疎まし。人え聞きつけで参らぬに、この女君いみじくわななき惑ひて、いかさまにせむと思へり。汗もしとどになりて、我かの気色なり。
「もの怖ぢをなむわりなくせさせ給ふ本性にて、いかに思さるるにか。」
と右近も聞こゆ。いとか弱くて、昼も空をのみ見つるものを、いとほしと思して、
「我人を起こさむ。手叩けば山彦の答ふる、いとうるさし。ここに、しばし、近く。」
とて、右近を引き寄せ給ひて、西の妻戸に出でて、戸を押し開け給へれば、渡殿の灯も消えにけり。風すこしうち吹きたるに、人はすくなくて、候ふかぎり皆寝たり。この院の預かりの子、睦ましく使ひ給ふ若き男、また上童一人、例の随身ばかりぞありける。召せば、御答へして起きたれば、
「紙燭さして参れ。随身も弦打ちして絶えず声づくれと仰せよ。人離れたる所に心とけて寝ぬるものか。惟光朝臣の来たりつらむは。」
と問はせ給へば、
「候ひつれど仰せ言もなし、暁に御迎へに参るべき由申してなむ、まかで侍りぬる。」
と聞こゆ。このかう申す者は、滝口なりければ、弓弦いとつきづきしくうち鳴らして、
「火危ふし。」
と言ふ言ふ、預かりが曹司の方に去ぬなり。内裏を思しやりて、名対面は過ぎぬらむ、滝口の宿直奏し今こそ、と推しはかり給ふは、まだいたう更けぬにこそは。
帰り入りて探り給へば、女君はさながら臥して、右近はかたはらにうつ伏し臥したり。
「こはなぞ、あなもの狂ほしのもの怖ぢや。荒れたる所は、狐などやうのものの人おびやかさむとて、け恐ろしう思はするならむ。まろあれば、さやうのものにはおどされじ。」
とて引き起こし給ふ。
「いとうたて乱り心地の悪しう侍れば、うつ伏し臥して侍るや。御前にこそわりなく思さるらめ。」
と言へば、
「そよ、などかうは。」
とてかい探り給ふに息もせず。引き動かし給へど、なよなよとして、我にもあらぬさまなれば、いといたく若びたる人にて、物にけどられぬるなめりと、せむ方なき心地し給ふ。紙燭持て参れり。右近も動くべきさまにもあらねば、近き御几帳を引き寄せて、
「なほ持て参れ。」
とのたまふ。例ならぬことにて、御前近くもえ参らぬつつましさに、長押にもえのぼらず。
「なほ持て来や。所に従ひてこそ。」
とて、召し寄せて見給へば、ただこの枕上に夢に見えつる容貌したる女、面影に見えてふと消え失せぬ。昔物語などにこそかかることは聞け、といとめづらかにむくつけけれど、まづ、この人いかになりぬるぞと思ほす心騒ぎに、身の上も知られ給はず添ひ臥して、
「やや。」
と驚かし給へど、ただ冷えに冷え入りて、息はとく絶え果てにけり。言はむ方なし。頼もしくいかにと言ひふれ給ふべき人もなし。法師などをこそはかかる方の頼もしきものには思すべけれど。さこそ強がり給へど、若き御心にて、言ふかひなくなりぬるを見給ふに、やる方なくて、つと抱きて、
「あが君、生き出で給へ、いといみじき目な見せ給ひそ。」
とのたまへど、冷え入りにたれば、けはひもの疎くなりゆく。右近は、ただあなむつかしと思ひける心地みな覚めて、泣き惑ふさまいといみじ。南殿の鬼のなにがしの大臣おびやかしける例を思し出でて、心強く、
「さりともいたづらになり果て給はじ。夜の声はおどろおどろし。あなかま。」
と諫め給ひて、いとあわたたしきにあきれたる心地し給ふ。
現代語訳
宵を過ぎる頃、(光源氏は)少しお眠りになっていると、枕もとにたいへん美しい様子の女が座って、
「私が(あなた様〔=光源氏〕を)たいへん立派だとお慕い申し上げている、その私を(あなた様は)訪ねようともお思いにならず、このような格別なとりえもない人(=夕顔)を連れておいでになってご寵愛なさるのが、大変気に食わずつろうございます。」
と言って、この(光源氏の)おそばに寝ている人(=夕顔)を抱き起こそうとすると(夢に)ご覧になる。
(光源氏は)物の怪に襲われたような心地がして、はっと目を覚まされたところ、明かりも消えてしまっていた。いやなことだとお思いになったので、(魔除けのために)護身用の太刀を引き抜いて(傍らに)お置きになって、右近をお起こしになる。
これ(=右近)も恐ろしいことと思っている様子で(光源氏の近くに)参上した。
「渡殿にいる宿直の者を起こして、紙燭をともして参れと言いなさい。」
と(右近に)おっしゃると、
「どうして退出しましょうか(、いや、できません)、暗くて。」
と言うので、
「おやおや、子どもっぽい。」
とお笑いになって、手をおたたきになると、こだまがこたえる音がひどく気味が悪い。
誰も聞きつけることができないで参上しないうえ、この女君(=夕顔)はたいそうひどく震えうろたえて、どうしようと思っている。汗もびっしょりになって、茫然自失し、生気を失った様子である。
「(夕顔様は)もの怖がりをむやみやたらになさるご性質ですので、どんなに(恐ろしく)お思いになっているでしょうか。」
と右近も(光源氏に)申し上げる。
(光源氏も夕顔が)ひどくか弱くて、昼間もただ空ばかりを眺めていたのに、かわいそうなこととお思いになって、(光源氏は)
「私が(行って)人を起こしてこよう。手をたたくとこだまがこたえるのが、実にわずらわしい。ここ(=夕顔のそば)に、ちょっとの間、そばに(いてくれ)。」
とおっしゃって、右近を(夕顔のそばに)引き寄せなさって、(光源氏は)西の妻戸に出て、戸を押し開けなさったところ、渡殿の明かりも消えてしまっていた。
風が少し吹いているうえに、(宿直の)人は少なくて、お仕えする人は全て皆寝込んでいる。この院の管理人の子で、(光源氏が)親しく召し使っておられる若い男と、上童一人と、(それに)いつもの随身(の三人)だけがいた。お呼びになると、(管理人の子が)お返事をして起きてきたので、
「紙燭をともして持って参れ。随身も弦打ちして絶えず警戒の声をたてよと命令せよ。(こんな)人気のない所で油断して寝るとは何事だ。惟光朝臣が来ていただろうが(どこへ行った)。」
とお尋ねになると、
「お仕えしていましたがご命令もない、暁にお迎えに参上しようという旨を申して、退出いたしました。」
と申し上げる。
このこう申し上げる者(=院の管理人の子)は、滝口の武士であったので、弓の弦をたいそう(この場に)ふさわしく打ち鳴らして、
「火の用心。」
と言い言い、管理人の部屋の方へ去って行くようだ。(光源氏はこの声を聞いて、)宮中に思いをはせられ、(今ごろは)名対面は過ぎただろう、宿直の滝口の武士の点呼はちょうど今ごろだろう、と推し量りなさるのは、まだあまり夜が更けていないのだろう。
(光源氏がもとの場所へ)引き返して手探りなさると、女君(=夕顔)はもとのままの状態で臥していて、右近が(その)そばにうつ伏せになっている。
「これは何ごとか、ああ見苦しいほどの怖がりようだなあ。荒れ果てている所は、狐などのようなものが人を脅かそうとして、恐ろしく思わせるのだろう。私が(ついて)いるからには、そんなものには脅されないぞ。」
とおっしゃって(右近を)引き起こしなさる。
(右近は)
「(私は)たいそう気味悪く取り乱した気分がすぐれませんので、うつ伏せになっていたのでございますよ。ご主人様(=夕顔)におかれてはむやみに怖がっていらっしゃるでしょう。」
と言うので、(光源氏は)
「そうそう、(夕顔は)どうしてこんなに(恐れるのか)。」
と言って手探りで探られると息もしていない。引き動かしなさっても、ぐったりとして、茫然としている様子なので、たいそうひどく子どもっぽい人なので、物の怪に正気を奪われてしまったようだと、どうしようもないお気持ちがなさる。
(そこに管理人の子が)紙燭を持って参上した。 右近も動けそうにない様子なので、(光源氏は自ら)近くの御几帳を引き寄せて(夕顔を隠し)、
「もっと近くに持って参れ。」
とおっしゃる。異例なことなので、(恐れ多く、光源氏の)おそば近くにも(管理人の子は)参上できない遠慮深さのため、(簀子と廂の間の)敷居にも上がることができない。
「もっと近くへ持ってこい。遠慮も場所次第だ。」
とおっしゃって、(紙燭を)お取り寄せになってご覧になると、ちょうどこの(夕顔の)枕もとに(先ほど)夢に現れた容貌をしている女が、幻に見えてすっとかき消えてしまった。
昔物語などでこそこういう話は聞いているが、とたいそう意外で気味が悪いけれど、まず、この人(=夕顔)がどうなったかとお思いになるご心配の胸騒ぎに、自分(=光源氏)の身の上について(何か厄介が起こるかもしれないということも)お考えになれないで(夕顔に)添い寝して、
「おいおい。」
とお起こしなさるけれども、(夕顔は)ひたすら冷たくなっていって、息はとっくに絶え果ててしまっていた。
(光源氏は)なんとも言いようがない。(ここには)頼りがいがあって、どうしたらいいかと相談なさることができる人もいない。 法師などこそこういう方面での頼りになるものとしてお思いになるはずだけれども。(光源氏は)あんなに強がっていらっしゃるけれど、(まだ)若いお心で、(夕顔が)亡くなってしまったのをご覧になると、どうしようもなくて、(夕顔を)じっと亡骸を抱いて、
「いとしい人よ、どうか生き返ってください、(私に)ひどく悲しい目をお見せにならないでください。」
とおっしゃるが、(夕顔は体温も)冷えきってしまっているので、様子がうす気味悪くなっていく。右近は、ただああ気味が悪いと思っていた気持ちがすっかり覚めて、激しく泣いて取り乱す様子は実に甚だしいほどだ。
紫宸殿の鬼が某大臣を脅かした(が、反対に追い払われた)例をお思い出しになって、心強く(思われ)、
「それでもむなしく死んでしまわれることはないだろう。夜の声は大げさに響く。しっ、静かに。」
と制止なさって、たいそう突然のできごとに途方に暮れている気持ちがなさる。
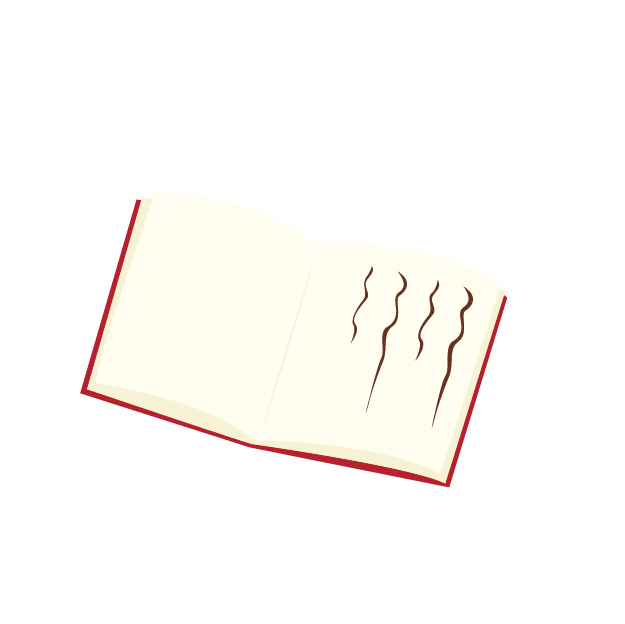

コメント