今回は『古今和歌集』の「仮名序」について解説していきたいと思います。
古今和歌集・文学史
選者
紀貫之・紀友則・凡河内躬恒・壬生忠岑
成立
905年
内容
最初の勅撰和歌集。巻頭に紀貫之の「仮名序」、巻末に紀淑望の「真名序」がある。
歌風は優美繊細な「たをやめぶり」。
歌風は三期に分けることができ、以下のような特徴がある。
第一期(詠み人知らずの時代)
「万葉集」の素朴さや五七調を残している。
第二期(六歌仙の時代)
六歌仙と呼ばれる歌人たちが代表的
- 大伴黒主
- 小野小町
- 在原業平
- 喜撰法師
- 文屋康秀
- 僧正遍昭
第三期(選者の時代)
優美で繊細な歌風。対象を理知的に詠み、技巧的で複雑な表現。
比喩・援護・掛詞などの修辞が巧みに用いられている。
本文
やまと歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。
世の中にある人、事業、繁きものなれば、心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひ出せるなり。
花に鳴く鶯、水にすむ蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌を詠まざりける。
力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男女の仲をも和らげ、猛き武士の心をも慰むるは、歌なり。
この歌、天地の開け始まりける時より出で来にけり。
しかあれども、世に伝はることは、ひさかたの天にしては下照姫に始まり、あらかねの地にしては素盞嗚尊よりぞ起こりける。
ちはやぶる神世には、歌の文字も定まらず、素直にして、事の心分きがたかりけらし。
人の世となりて、素盞嗚尊よりぞ、三十文字あまり一文字は詠みける。
かくてぞ花をめで、鳥をうらやみ、霞をあはれび、露を悲しぶ心・言葉多く、さまざまになりにける。
遠き所も、出で立つ足下より始まりて年月を渡り、高き山も、麓の塵泥よりなりて天雲棚引くまで生ひ上れるごとくに、この歌もかくのごとくなるべし。
現代語訳
和歌は、人の心を種として(それから生まれ)、さまざまな言葉となっていった。
この世で生きる人は、関わり合ういろいろなことが多いものなので、心に思うことを、見るもの聞くものに託して言い表したのである。
花(の間)で鳴く鶯、水にすむカジカの声を聞くと、この世で生きているもの全ての中で、どれが歌を詠まなかったか。いや、全てが歌を詠んだ。力を入れないで天地を動かし、目に見えない鬼や神を感動させ、男女の仲を親密にし、荒々しい武士の心をも慰めるのは、歌である。
この歌は、天地が分かれた時から生まれた。そうではあるが、世に伝わることについては、天上の世界では下照姫(の時代)に始まり、地上の世界では素盞嗚尊から始まった。
神々の時代では、歌の音数も一定せず、飾り気がなくて、歌の意味もはっきりとは理解しにくかったらしい。
(それが)人の世となって、素盞嗚尊の時から、三十一文字(の歌)を詠むことになった。こうして花を愛し、鳥のようでありたいと願い、霞に情趣を感じ、露を賞美する心や言葉は多く、(それを詠んだ歌も)さまざまになった。
遠方(への旅)も、出発の第一歩から始まって長い年月にわたり、高い山(ができあがるの)も、麓の塵や泥(の積もったもの)からでき空の雲のたなびく高さまで成長しているように、この歌もこのように発達したのであろう。
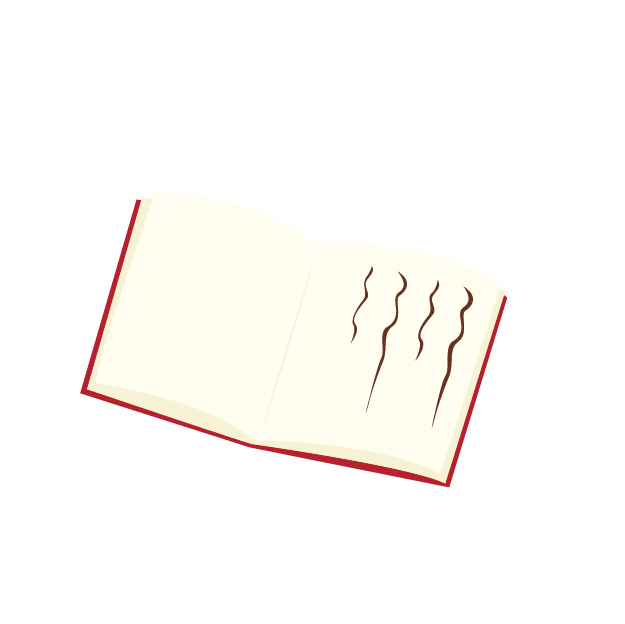

コメント