文学史
作者
信濃前司行長か?
成立
1221年ごろ
ジャンル
軍記物語
内容
平清盛を中心とした平家一族の栄華と横暴、清盛死後の木曽義仲による平家の都落ち、源義経による壇ノ浦での平家の滅亡を描く。
文章は典型的な和漢混交文で、琵琶法師によって「平曲」として語られた。
本文
木曽左馬頭、その日の装束には、赤地の錦の直垂に唐綾縅の鎧着て、鍬形打つたる甲の緒締め、
いかものづくりの大太刀はき、石打ちの矢の、その日のいくさに射て少々残つたるを、
頭高に負ひなし、滋籐の弓持つて、聞こゆる木曽の鬼葦毛といふ馬の、
きはめて太うたくましいに、黄覆輪の鞍置いてぞ乗つたりける。
鐙ふんばり立ち上がり、大音声をあげて名のりけるは、
「昔は聞きけんものを、木曽の冠者、今は見るらん、左馬頭兼伊予守、朝日の将軍源義仲ぞや。甲斐の一条次郎とこそ聞け。互ひによいかたきぞ。義仲討つて兵衛佐に見せよや。」
とて、をめいて駆く。一条次郎、
「ただ今名のるは大将軍ぞ。あますな者ども、もらすな若党、討てや。」
とて、大勢の中に取りこめて、我討つ取らんとぞ進みける。
木曽三百余騎、六千余騎が中を、縦様・横様・蜘蛛手・十文字に駆け割つて、
後ろへつつと出でたれば、五十騎ばかりになりにけり。
そこを破つて行くほどに、土肥次郎実平二千余騎でささへたり。
それをも破つて行くほどに、あそこでは四、五百騎、ここでは二、三百騎、百四、五十騎、百騎ばかりが中を、駆け割り駆け割り行くほどに、主従五騎にぞなりにける。
五騎がうちまで巴は討たれざりけり。木曽殿、
「おのれはとうとう、女なれば、いづちへも行け。我は討ち死にせんと思ふなり。もし人手にかからば自害をせんずれば、木曽殿の最後のいくさに、女を具せられたりけりなんど言はれんことも、しかるべからず。」
とのたまひけれども、なほ落ちも行かざりけるが、あまりに言はれたてまつりて、
「あつぱれ、よからうかたきがな。最後のいくさして見せたてまつらん。」
とて、控へたるところに、武蔵の国に聞こえたる大力、御田八郎師重、三十騎ばかりで出で来たり。
巴、その中へ駆け入り、御田八郎に押し並べて、むずと取つて引き落とし、わが乗つたる鞍の前輪に押しつけて、ちつともはたらかさず、首ねぢ切つて捨ててんげり。
そののち、物具脱ぎ捨て、東国の方へ落ちぞ行く。手塚太郎討ち死にす。手塚別当落ちにけり。
今井四郎、木曽殿、主従二騎になつて、のたまひけるは、
「日ごろは何ともおぼえぬ鎧が、今日は重うなつたるぞや。」
今井四郎申しけるは、
「御身もいまだ疲れさせたまはず、御馬も弱り候はず。何によつてか、一領の御着背長を重うはおぼしめし候ふべき。それは、御方に御勢が候はねば、臆病でこそさはおぼしめし候へ。兼平一人候ふとも、余の武者千騎とおぼしめせ。矢七つ八つ候へば、しばらく防き矢つかまつらん。あれに見え候ふ、粟津の松原と申す、あの松の中で御自害候へ。」
とて、打つて行くほどに、また新手の武者、五十騎ばかり出で来たり。
「君はあの松原へ入らせたまへ。兼平はこのかたき防き候はん。」
と申しければ、木曽殿のたまひけるは、
「義仲、都にていかにもなるべかりつるが、これまで逃れ来るは、なんぢと一所で死なんと思ふためなり。ところどころで討たれんよりも、ひとところでこそ討ち死にをもせめ。」
とて、馬の鼻を並べて駆けんとしたまへば、
今井四郎、馬より飛び下り、主の馬の口に取りついて申しけるは、
「弓矢取りは、年ごろ日ごろいかなる高名候へども、最後のとき不覚しつれば、長き疵にて候ふなり。御身は疲れさせたまひて候ふ。続く勢は候はず。かたきに押し隔てられ、言ふかひなき人の郎等に組み落とされさせたまひて、討たれさせたまひなば、『さばかり日本国に聞こえさせたまひつる木曽殿をば、それがしが郎等の討ちたてまつたる。』なんど申さんことこそ、くちをしう候へ。ただあの松原へ入らせたまへ。」
と申しければ、木曽、
「さらば。」
とて、粟津の松原へぞ駆けたまふ。
今井四郎ただ一騎、五十騎ばかりが中へ駆け入り、鐙ふんばり立ち上がり、大音声あげて名のりけるは、
「日ごろは音にも聞きつらん、今は目にも見たまへ。木曽殿の御乳母子、今井四郎兼平、生年三十三にまかりなる。さる者ありとは、鎌倉殿までも知ろしめされたるらんぞ。兼平討つて見参に入れよ。」
とて、射残したる八筋の矢を、さしつめ引きつめさんざんに射る。
死生は知らず、やにはにかたき八騎射落とす。
そののち打ち物抜いて、あれに馳せ合ひ、これに馳せ合ひ、切つてまはるに、面を合はする者ぞなき。ぶんどりあまたしたりけり。ただ
「射とれや。」
とて、中に取りこめ、雨の降るやうに射けれども、鎧よければ裏かかず、あき間を射ねば手も負はず。
木曽殿はただ一騎、粟津の松原へ駆けたまふが、正月二十一日、入相ばかりのことなるに、
薄氷は張つたりけり、深田ありとも知らずして、馬をざつと打ち入れたれば、
馬の頭も見えざりけり。
あふれどもあふれども、打てども打てども、はたらかず。
今井が行方のおぼつかなさに、ふりあふぎたまへる内甲を、三浦の石田次郎為久、
追つかかつて、よつぴいて、ひやうふつと射る。
痛手なれば、真向を馬の頭にあててうつぶしたまへるところに、石田が郎等二人落ち合うて、
つひに木曽殿の首をば取つてんげり。
太刀の先に貫き、高くさし上げ、大音声をあげて、
「この日ごろ日本国に聞こえさせたまひつる木曽殿をば、三浦の石田次郎為久が討ちたてまつりたるぞや。」
と名のりければ、今井四郎、いくさしけるが、これを聞き、
「今は、たれをかばはんとてかいくさをもすべき。これを見たまへ、東国の殿ばら、日本一の剛の者の自害する手本。」
とて、太刀の先を口に含み、馬よりさかさまに飛び落ち、貫かつてぞ失せにける。
さてこそ粟津のいくさはなかりけれ。
現代語訳
木曽左馬頭は、その日の装束としては、赤地の錦の鎧直垂の上に唐綾縅の鎧を着て、
鍬形を打ちつけてある甲の緒を締め、いかめしい作りの大太刀を腰に差し、
石打ちの矢で、その日の合戦に射て少々残っているのを、
頭上高く突き出るようにして背負い、滋籐の弓を持って、
評判の高い木曽の鬼葦毛という馬で、非常に太くたくましいのに、
黄覆輪の鞍を置いて乗っていた。
鐙をふんばり立ち上がり、大声を上げて名のったことには、
「以前は聞いただろうが、木曽の冠者を、今は見ているだろう、左馬頭兼伊予守、朝日の将軍源義仲だぞ。(おまえは)甲斐の一条次郎と聞く。互いに不足ない敵だぞ。義仲を討って頼朝に見せろよ。」
と言って、大声を上げて馬に乗って走る。
一条次郎は、
「ただ今名のるのは総大将だぞ。逃すな者どもよ、討ちもらすな若党よ、討てよ。」
と言って、大軍の中に(義仲を)取り囲んで、自分が討ち取ろうと(我先に)進んだ。
木曽の三百余騎は、(一条の)六千余騎の中を、縦・横・蜘蛛手・十文字に自在に駆け通って、
(一条軍の)背後にさっと出たところ、五十騎ほどになってしまった。
そこを破って行くうちに、土肥次郎実平が二千余騎で陣を張っている。
それをも破って行くうちに、あそこでは四、五百騎、
ここでは二、三百騎、百四、五十騎、百騎ほどの中を、駆け抜け駆け通りして行くうちに、主従五騎になってしまった。
五騎の中まで巴は討たれず残っていた。
木曽殿は、
「そなたは早く早く、女なのだから、どこへでも行け。俺は討ち死にしようと思うのだ。もし敵の手にかかっ(て傷を負)ったら自害をするつもりなので、(いずれにしても死ぬのだ。)木曽殿が最後の合戦に、女をお連れになったそうだなどと(世間で)言われるようなことは、ふさわしくない。」
とおっしゃったけれども、(巴は)なおも逃げ落ちて行かなかったが、
あまりに(繰り返し)言われ申して、
「ああ、相手に不足ない敵がいるといいなあ。最後の合戦をしてお目にかけよう。」
と言って、馬を引き止めて待機しているところに、
武蔵の国に知られている大力の、御田八郎師重が、三十騎ほどで出て来た。
巴は、その中に馬で駆け入り、御田八郎に無理に並べて、むんずと組みついて引き落とし、
自分が乗っている鞍の前輪に(八郎を)押しつけて、少しも身動きさせず、首をひねり切って捨ててしまった。
そののちに、武具を脱ぎ捨て、東国のほうへ離脱して行く。
手塚太郎は討ち死にする。手塚別当は去って行った。
今井四郎と、木曽殿は、主従二騎となって、(木曽殿の)おっしゃったことには、
「日ごろは何とも感じない鎧が、今日は重くなったよ。」
と。今井四郎が申したことには、
「お体もまだお疲れではありません、お馬も弱っていません。なぜ、一着の大鎧を重くはお感じになるのでしょうか、そんなはずはありません。それは、味方に軍勢がございませんので、気おくれのためにそうお思いなのです。兼平は(ただ)一人おりましても、他の武者千騎(と同じ)とお思いください。矢が七、八本ありますので、しばらく防ぎ矢をいたしましょう。あれに見えます、粟津の松原と申す、あの松の中でご自害なさい。」
と言って、馬にむち打って進むうちに、また新しい武士の一隊が、五十騎ほどで出て来た。
(今井が)「殿はあの松原へお入りなさい。兼平はこの敵を防ぎましょう。」
と申したところ、木曽殿がおっしゃったことには、
「義仲は、都で最期を遂げるはずだったが、ここまで逃げて来たのは、おまえと一つ所で死のうと思うためなのだ。別々の所で討たれるよりも、同じ所で討ち死にをしよう。」
と言って、馬の鼻を並べて走ろうとなさるので、今井四郎は、馬から飛び下り、主君の馬の轡にしがみついて申し上げたのは、
「武士というものは、幾年月の間どんな軍功がございましても、最後のときに失敗してしまうと、末代までの不名誉でございます。お体は疲れていらっしゃいます。あとに続く味方はございません。(二人の間を)敵に無理やり隔てられ、取るに足らない下っ端武士に馬から組み落とされなさって、お討たれになってしまったら、『あれほど日本国中に評判でいらっしゃった木曽殿を、誰それの郎等がお討ち申し上げたよ。』などと名のり申すようなことが、残念でございます。ただもうあの松原へお入りください。」
と申したので、木曽は、
「そういうことなら。」
と言って、粟津の松原へ馬で急ぎなさる。
今井四郎はただ一騎で、五十騎ほどの(敵の)中に駆け入り、鐙をふんばり立ち上がり、
大声を上げて名のったのは、
「日ごろは評判にきっと聞いているだろう、今は目でも見たまえ。(俺は)木曽殿のご後見役の子、今井四郎兼平、三十三歳になり申す。そういう者がいるとは、頼朝殿までもご存じでいらっしゃるだろうよ。兼平を討って(首を)御覧に入れろ。」
と言って、射残していた八本の矢を、やつぎばやにどしどしと射る。
死んだか息のあるかはわからないが、その場ですぐに敵八騎を射落とす。
矢がなくなったあとは刀を抜いて、あちらこちらと馬を走らせ敵に当たり、切ってまわるので、正面から立ち向かう者もいない。
大勢の敵を殺傷してしまった。
ただ
「射殺せよ。」
と言って、中に取り囲み、雨が降るように射たけれども、(今井の)鎧がよいので矢が裏まで通らず、鎧の隙間を射ないので傷を負うこともない。
木曽殿はただ一騎で、粟津の松原へ馬で走って行かれたが、
正月二十一日の、夕暮れ時のことなので、薄氷は張っていたし、
深い泥田があるともわからずに、馬をざっと打ち入れたところ、馬の頭も見えなかった。
どんなに馬の脇腹を蹴っても、どんなに馬の尻をむち打っても、動かない。
今井がどうなったかが気がかりで、振り仰ぎなさった甲の内側を、三浦の石田次郎為久が、追いついて、弓をぐっと引きしぼって、矢をひょうふっと射る。
重傷なので、甲の正面を馬の頭に当ててうつぶしなさったところに、石田の郎等が二人(駆けつけて)落ち合って、とうとう木曽殿の首を取ってしまった。(首を)太刀の先に貫き、高くさし上げ、大声を上げて、
「この日ごろ日本国中に評判でいらっしゃった木曽殿を、三浦の石田次郎為久がお討ち申したぞ。」
と名のったところ、今井四郎は、戦っていたが、これを聞き、
「今となっては、誰をかばおうとして戦う必要があろうか。これを見たまえ、東国の殿方よ、日本一の勇猛の武士が自害する見本を。」
と言って、太刀の先を口に含み、馬から逆さまに飛び落ち、(刀が体を)突き通って死んでしまった。
こうして粟津の戦いは終わったのだった。
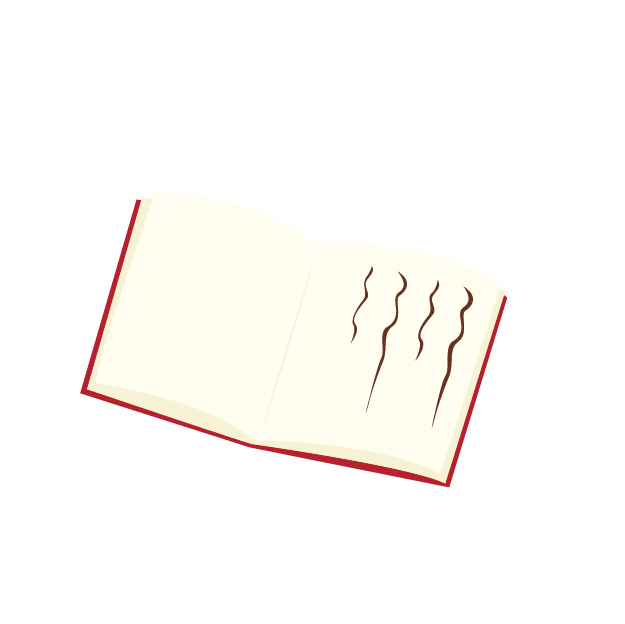

コメント